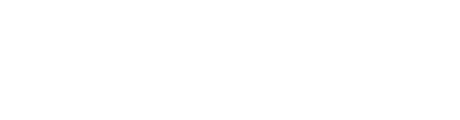※この記事は、広告を含む場合があります。

自己破産を考えているのですが、手続きの種類が多くて自分がどの手続きに当たるのかわかりません。。。

自己破産の手続きには、管財手続きと同時廃止手続きの2種類があります。
さらに、管財手続きのなかでも通常の管財手続きと、少額管財手続きがあります。それぞれの違いを特徴や期間、費用とあわせて解説します。
管財手続き

処分すべき財産のある債務者が自己破産手続きをした場合、管財手続き(管財事件)となります。
もともと、自己破産は破産手続きをした債務者(破産人)の持っている財産を処分してお金に変えて、債権者に平等に分配する債務整理方法です。
そのため、自己破産の原則的な手続きは管財手続きになります。
管財手続きには以下の特徴があります。
- 破産人が評価額20万円以上の財産を持っている
- 法人の代表または個人事業主
- 債務額が約5,000万円以上
- 裁判所によって判断が異なる
- 残った債務は免責手続きをする
- 同時廃止に比べると費用と時間がかかる
管財手続きは、破産する人が借入先にお金を分配できそうな財産を所有している場合が該当します。
同時廃止となるか管財手続きとなるかは自分で選ぶ訳ではなく、裁判所が決定します。
具体的には、20万円以上の財産を持っている場合は、管財手続きとなる可能性が高いです。
注意が必要なのは、破産する人が持っている財産の合計が20万円以上ではなく、財産の中のどれか1つでも20万円以上の財産を持っている場合が該当します。
たとえば、貯金が15万円、株等で10万円を所有している場合、合計額では20万円以上ですがそれぞれは20万円に満たないため、管財手続きにはなりません。
なお、破産人が社長だったり個人事業主の場合、もしくは借金総額が約5,000万円以上の場合は財産の有無に関係なく管財手続きとなります。
財産を処分して分配後、借金が残った場合は破産手続きと別に免責手続きを行い、返済しなければならないか、免責になるかが決められます。
財産の調査や処分、分配を行うのは弁護士資格を持つ破産管財人です。破産管財人がひとつひとつ財産を調査し、換金、分配の手続きをするため管財手続きは手続き完了まで時間がかかります。
また、破産管財人への報酬もかかるため、他の手続きと比べて費用も高くなります。
費用の相場
約70万円~(予納金や官報公告費など裁判所への費用50万円~、弁護士や司法書士への依頼費用20万円~)
かかる期間
準備期間だけで短くて1カ月~、長くて半年
財産や残務の額、事業内容などによって長期化する可能性が高い。
同時廃止手続き

債務者に処分すべき財産がない場合は、同時廃止手続きとなります。
債務者に処分すべき財産がない場合は、自己破産手続きの開始とともに手続き終了(破産手続き廃止)となるため、同時廃止と呼ばれています。処分すべき財産がないため、破産管財人は必要なくなります。
管財手続きとなるか、同時破産手続きとなるかは裁判所の判断によります。
ただし、自己破産の手続きは多いため、件数の多い東京地検などでは即日面接というシステムを取っています。
即日面接とは、申立てをした日に弁護士と裁判官が面接をし、管財手続きか同時廃止手続きかが振り分けられます。
同時廃止手続きとなるとその場で手続き終了となるため、自己破産をした当日に手続きが終了となるのです。
同時廃止手続きは、管財手続きよりも費用も時間もかかかりません。ただし、同時廃止手続きとなっても、免責手続きは必要です。
破産手続で支払われなかった債務は、免責手続きによって支払いの義務があるか、免責となるかが決められます。
費用の相場
約30万円~(予納金や官報公告費など裁判所への費用1~5万円、弁護士や司法書士への依頼費用20万円~)
かかる期間
準備期間は最低1~2カ月、長いと半年
申立てから免責まで3~4カ月。
少額管財手続き

管財手続きにかかる費用は高いため、費用面でいつまでたっても債務整理ができず経済的な更生ができない場合があります。
手続きを簡略化することで、予納金を少なくした手続きが少額管財手続きです。
少額管財手続きを受けるには、条件として弁護士に依頼して裁判の手続きや財産の調査を代行してもらう必要があります。
そのため、少額管財手続きはほかの自己破産手続きと異なり、司法書士は代行できません。
管財手続きよりも、費用やかかる期間をおさえられるメリットがあります。
なお、少額管財手続きが利用できる債務状態でも、自分で手続きをしたり、司法書士に依頼したりした場合は管財手続きとなります。
少額管財手続きは、東京地裁をはじめ都市部での裁判所で取り入れている傾向にあります。
・費用の相場
約50万円~(予納金や官報公告費など裁判所への費用20万円~、弁護士や司法書士への依頼費用20万円~)
・かかる期間
準備期間は最低1~2カ月、長いと半年
申立てから免責まで約4カ月。
まとめ
自己破産は財産の有無によって管財手続きか同時廃止手続きになります。
どちらになるかは裁判所の裁量によって決定されますが、20万円以上の財産がある、法人の代表または個人事業主、5,000万円以上の負債がある場合は管財手続きとなる可能性が高いです。
管財手続きは破産管財人による調査や財産の分配が行われるため、費用も期間も同時廃止手続きよりもかかります。
管財手続きの高額費用の支払いができず自己破産手続きができない場合には、少額管財手続きを利用するのが選択肢です。
費用面で自己破産ができずに借金問題が解決しない、自己破産手続きで管財手続きか同時廃止手続きかどうなるかわからないときには、弁護士へ相談してみましょう。
自己破産もふくめて、ベストな方法で借金整理のアドバイスが受けられます。借金問題を解決したいときには弁護士の力を借りて、経済的な更生を目指しましょう。